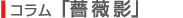
(毎月2回更新)
第10回 本歌取り二つ
竹久夢二の「宵待草」の「待てど暮らせど来ぬ人を/宵待草のやるせなさ」の本歌が、藤原定家の「来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ」であることは、夢二と彼の作品をふまえつつ彼の生きたこの国の近代という時代を書いた長編詩『夢ふたたび』のあとがきで指摘した。本歌取りというのは、和歌の修辞法(レトリック)の一つだが、新古今和歌集においては古典尊重という時代精神が要求する方法であった。夢二の場合はどうだったろう。彼は一体何を待っていたか。そして時代は。
正岡子規の「春や昔一五万石の城下哉」の本歌は在原業平の「月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身ひとつはもとの身にして」だ。古今集嫌い古今集嫌い、紀貫之嫌いが子規の写生説主張の戦略であったことを、垣間見せる。(9月25日)